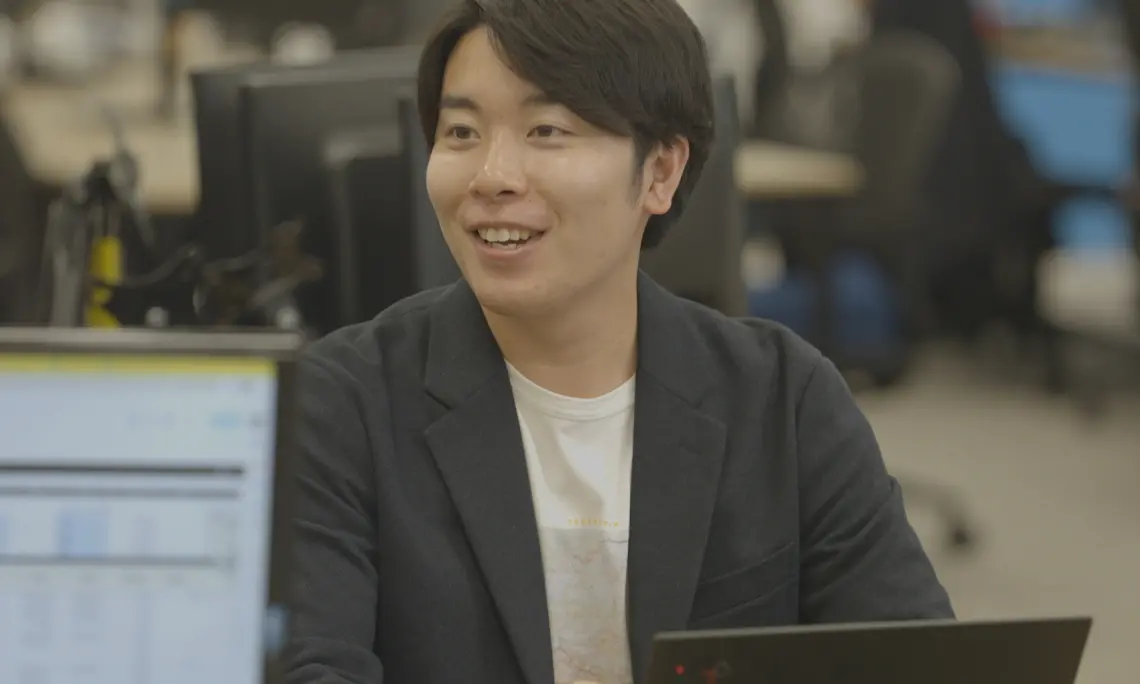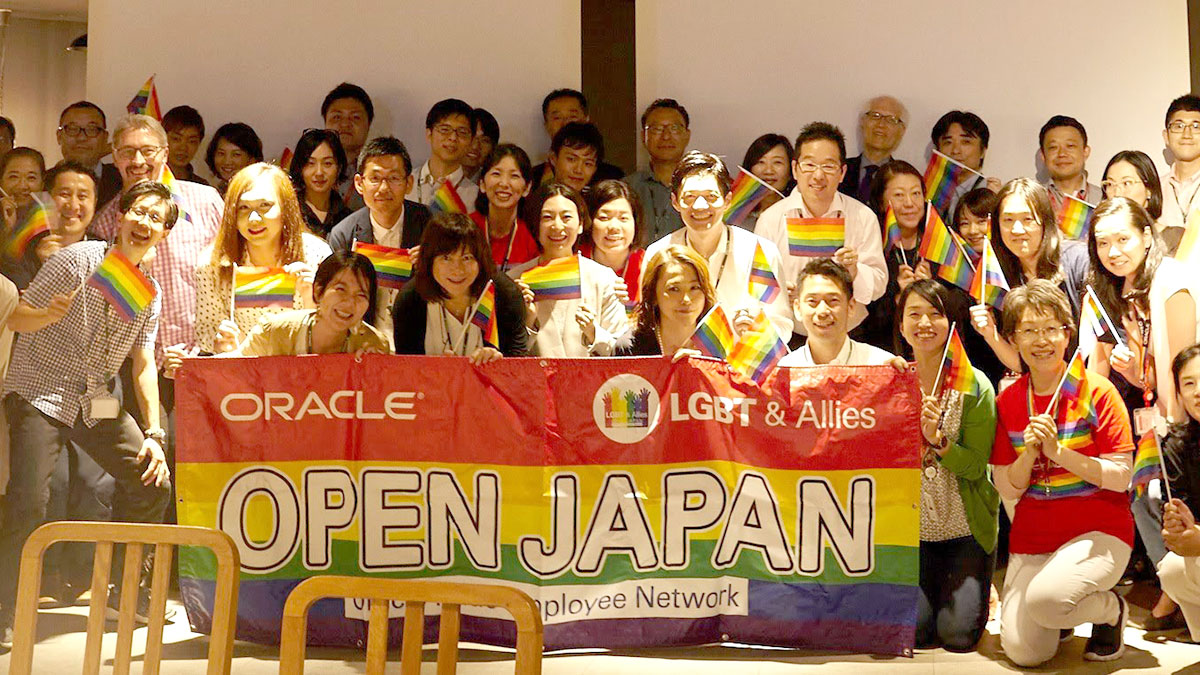SCROLL
エージェントは、
社会の「困った」を
事業で解決しようと試みる
挑戦者の集まりです。

身近な誰かの「困った」を解決したいという、強い想い。
事業として欠かせない収益を諦めない、仕組みづくり。
社会、生活者、取引先、働く自分たち
あちこちに視点を飛ばして、想像と対話を重ねながら、みんなが笑顔になれる事業をデザインしていく。

ゲームに熱中する子供のように没頭して、
仲間と協力しながら、失敗と挑戦を繰り返し、
ふと気が付くと、これまで歩んできた道のりが
誰かの笑顔と、自分のキャリアに変わっている。
それが、エージェントでの働き方です。
仲間と協力しながら、失敗と挑戦を繰り返し、
ふと気が付くと、これまで歩んできた道のりが
誰かの笑顔と、自分のキャリアに変わっている。
それが、エージェントでの働き方です。
どうです?
ちょっとワクワクしませんか?